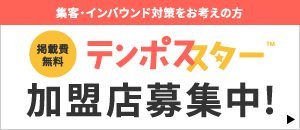ランキング
2024/08/05
山形のご当地B級グルメ「さくらんぼ」の特徴や歴史を紹介!

この記事の目次
初夏の訪れを告げる「さくらんぼ」といえば山形県が有名です。全国の収穫量の7割以上を占め、日本一の生産量を誇る山形県。東根市、天童市、寒河江市などの地域では、美しい山々を背景に広がるさくらんぼ畑が広がっています。
見た目がかわいく、甘酸っぱい味で誰からも愛されているさくらんぼ。
そんなさくらんぼの特徴や歴史について探っていきましょう。
山形県のさくらんぼの特徴

「果樹園の宝石」ともよばれるさくらんぼ。ルビー色の美しい見た目と栽培のむずかしさからそうよばれています。そんな栽培困難なさくらんぼの生産量で日本一を誇るのが山形県。
さくらんぼは、寒い冬を越えて休眠することで実をつけ、暑い夏を過ごすことで花芽が充実して、次の年の着果がよくなります。山形県の気候は、梅雨時の湿気と雨が少なく、夏は猛暑、冬は積雪が多いという特徴があり、さくらんぼの栽培に最適でした。
また、生産者たちの惜しまぬ努力がさくらんぼをより一層おいしくしています。2月ごろの剪定作業や3月の花芽の間引き、霜対策や毛バタキを使用した手作業での受粉など、生産者たちが多くの手間をかけてさくらんぼを育てているのです。
5月下旬から7月初旬の収穫期には、手早く慎重に収穫し、美しく箱詰めされたさくらんぼが市場に出回ります。
山形には、ジューシーでさっぱりとした甘さの「南陽」、甘酸っぱく赤肉の「紅さやか」、甘みが濃くしっかりした果肉の「紅秀峰」、大粒で味が濃厚な「紅てまり」、鮮やかな赤色の「紅きらり」、果汁が多く早生の「紅ゆたか」など、さまざまな品種があります。特に人気なのが「佐藤錦」。甘みと酸味のバランスが絶妙で、やわらかい食感が特徴です。
山形県のさくらんぼの歴史
さくらんぼの原産地は、西南アジア地方とされ、自然に育ち、人々や鳥などに食べられ広まったといわれています。
さくらんぼが日本に渡来したのは明治元年(1868年)、そして山形県に持ち込まれたのは明治8年(1875年)。当時、全国でさくらんぼの栽培が試みられましたが、多くの地域で霜害や梅雨、台風などの被害により失敗しました。そんななか被害が少なかった山形県では、さくらんぼの栽培に成功しました。
さくらんぼの育ての親として知られているのは、本多成充です。明治21年(1888年)、山形県寒河江市の本多成允と渡辺七兵衛が中心となり、農産物試験場を設立し、キャベツやじゃがいも、りんごやさくらんぼなどの西洋野菜の研究をはじめます。
本多成允は、自分の畑に何種類かのさくらんぼを植えてみたところ、水はけのよい畑にさくらんぼが適していることを発見します。そこで、苗木を農家の人たちに分け与え、栽培するようにすすめました。
明治28年(1895年)ごろには、品種も増え、生産量も増加しました。日持ちしないさくらんぼをより多くの方に届けるため、井上勘兵衛が缶詰を開発し、横浜まで販売しました。
さくらんぼのなかで注目したいのは、最高品種の「佐藤錦」です。生みの親である東根市の篤農家・佐藤栄助は、さくらんぼの品種改良に情熱を注いでいました。明治時代「日の出」「珊瑚」「若紫」などを栽培していましたが、収穫しても日持ちが悪くて腐らせてしまったり、出荷の途中で傷んでしまったりと、悩みが多かったからです。
そこで、大正元年(1912年)に、日持ちがよくないが味のいい「黄玉」と、酸味が多いが固くて日持ちのいい「ナポレオン」を交配させました。初めて実を結んだのは、10年後の大正11年(1922年)。
「味も日持ちもよく、育てやすいさくらんぼ」の実ができたので、一本にしぼり原木にすることにします。大正元年から苦節16年、この新しい品種は「佐藤錦」と名付けられ、見事な味と日持ちのよさから、山形県のさくらんぼの代表品種となりました。
「佐藤錦」と名付けたのは、佐藤栄助の友人であり苗木商を営んでいた岡田東作です。命名するとき、佐藤栄助は「出羽錦」との案を出したのですが、岡田東作が「発見者の名前を入れた『佐藤錦』がいい」と提案して決まったというエピソードが残っています。
その後、佐藤錦は少しずつ出荷量を伸ばし、昭和50年(1975年)ごろから生食用の需要が高まり一気に全国区に躍り出ました。また、同じころから本格化した雨よけハウスの導入により、生食に適した完熟したさくらんぼの生産が可能となったことも、急激な生産拡大につながったとされています。
「さくらんぼ王国」とまでよばれるようになった山形には、さくらんぼを求めて多くの観光客が訪れるようになりました。
山形県の観光情報とアクセス方法
さくらんぼが有名な山形には、さまざまな観光スポットがあります。今回は、山形にある3つの人気観光スポットを紹介します。
天童公園

さまざまな絶景が楽しめる「天童公園」。天童市の中心部にある舞鶴山全体が公園となっています。山頂の展望広場からは月山や朝日連峰、最上川など山形を代表する自然の美しさが一望できます。
桜の名所として知られていて、4月中旬には約2,000本の桜が咲き乱れます。また、天童桜まつりも必見です。甲冑や着物姿に身を包んだ人々が自ら将棋の駒となって戦う「人間将棋」が開催されます。園内にはツツジやアジサイ、モミジなど、四季折々の花々が咲き、季節を通して散策が楽しめます。
玉簾の滝

高さ63m、幅5mの「玉簾の滝」は、約1200年前に弘法大師が発見・命名したといわれています。断崖絶壁から勢いよく流れ落ちる滝の光景は、美しく圧倒されます。
特におすすめなのは、ゴールデンウィークとお盆の時期に行われる夜間ライトアップ。昼間とはまた違った幻想的な光景が広がります。また、1月下旬から2月中旬にかけて滝が凍りつく「氷瀑」というめずらしい光景も必見です。迫力満点の自然の美しさを堪能できます。
鶴岡市立加茂水族館

山形県唯一の水族館「鶴岡市立加茂水族館」は「クラゲドリーム館」ともよばれるほどクラゲの展示が充実しています。展示されているクラゲは、なんと60種類以上です。「クラゲドリームシアター」では、夢の世界を体験できます。直径約5mの巨大な水槽の中で約10,000匹のミズクラゲが青くライトアップされたなかを漂う姿は、とても幻想的です。
クラゲだけではなく、地元庄内の魚やアシカ、アザラシも見ることができます。クラゲ料理が楽しめるレストランも併設されている人気の観光スポットです。
グルメも観光も魅力的な山形には、さまざまなアクセス方法があります。日本三大都市でもある東京、大阪、名古屋からのアクセスも便利です。東京、大阪、名古屋からなら飛行機で向かえば約1時間で到着します。
車でゆっくりドライブを楽しみながら山形に向かうのもおすすめです。最適なアクセス方法を探してみてくださいね。
まとめ
山形の自然と生産者の愛情が詰まったさくらんぼは、一度は食べたい味わいです。そのままでもおいしいさくらんぼですが、さくらんぼを使った料理やデザートも必見です。
山形に訪れた際は、さくらんぼをぜひ食べてみてくださいね。
\ テンポススター加盟店を募集中! /