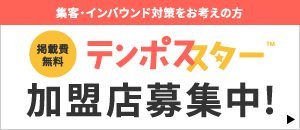ランキング
2025/01/01
三重県のご当地B級グルメ「伊勢エビ」とは?特徴や歴史を紹介!

この記事の目次
日本一の漁獲量を誇る三重県の伊勢海老は、「三重県のさかな」にも選ばれるほど、地域に深く根付いた存在です。その真紅の体と濃厚な味わいは、多くの人々を魅了し続けています。
そんな伊勢エビの特徴と歴史について探っていきましょう。
伊勢エビの特徴

伊勢エビの旬は10月から4月。新鮮な味わいを楽しむなら、お刺身がおすすめです。透き通るような身は、ぷりっとした弾力があり、噛むほどに上品な甘みが広がります。このほかにも、伊勢エビの旨みを堪能できる味噌汁や、香ばしい香りが食欲をそそる直火焼きなど、さまざまな調理法で楽しめます。
伊勢エビが生息するのは、熊野灘の浅い岩礁域。川から流れ込む豊富な栄養と沖合からの黒潮が、この海域に豊かな餌をもたらし、ぷりぷりとした身の弾力と甘みを育んでいます。
伊勢エビの生態も興味深いものです。初夏に産卵した卵から孵化するのは、親とは似ても似つかないフィロゾーマ幼生。この幼生は約1年間海中を漂い、その後、透明なプエルルス幼生へと変化します。脱皮を重ね、体長約2cmのエビとなり、成長すると最大30cmにまで達します。昼間は岩陰に潜み、夜行性の習性を活かしてウニや貝を食べながら大きくなります。
伊勢エビの歴史
日本では、縄文時代から海老が食べられていたとされており、天平5年(733年)の文献「出雲風土記」には、海老の記述が残されています。
特に伊勢エビが注目されるようになったのは、室町時代以降のことです。このごろ、武家の婚礼や祝宴に伊勢エビが欠かせない存在となり、長いヒゲと曲がった腰が長寿の象徴として重んじられるようになりました。その真紅の体も相まって、伊勢エビは縁起物としての地位を確立しました。ただし、当時の伊勢エビは非常に高価で、庶民にとっては遠い存在でした。
江戸時代になると、江戸前(東京湾)でクルマエビや芝エビが漁獲されるようになり、寿司や天ぷらといった料理にエビが使われはじめ、庶民も食べられるようになりました。それでも伊勢エビは特別な存在であり続け、祝宴を彩る高級食材として位置づけられていました。
伊勢エビという名前の由来にはさまざまな説があります。江戸時代の古書『大和本草』には、「此の海老、伊勢より来る故、伊勢海老と号す」と記されています。かつて伊勢地方から京都へ多くの産物が運ばれたことが、地名に由来する説の根拠とされています。
このほかにも、伊勢エビの甲殻が武士の甲冑に似ていることから「威勢のよい海老」と名付けられた説や、産卵期に磯で多く見られることから「磯海老」がなまって「伊勢エビ」となったという説もあります。
伊勢エビを支える三重県の取り組み
三重県では厳しい保護規制を実施し、伊勢エビの持続可能な漁業を目指しています。漁期を5月から9月まで禁漁とし、規定サイズ以下のエビは放流するなどの取り組みが行われています。さらに、年間2万匹以上の幼い伊勢エビを放流するなど、漁師たちの努力が安定した漁獲量を支えています。
伊勢エビ漁には、熟練の技術と細やかな配慮が欠かせません。刺し網漁では、一匹ずつ丁寧に扱い、傷つけないよう網から外します。また、三重県の漁協では、「三重ブランド」のタグを触角に装着し、品質と産地を保証しているため、安心して手に取ることができます。
移動範囲が狭く高価である伊勢エビは、栽培漁業の対象として期待されています。三重県は、昭和63年(1988年)に世界で初めて伊勢エビの卵から稚エビまでの人工飼育に成功しました。この成果は、明治32年(1899年)から始まった稚エビの人工育成への挑戦が実を結んだもので、約91年にわたる努力の結晶です。現在では小規模な飼育技術が確立され、将来的にはより大規模な稚エビの生産が目指されています。
伊勢エビは、地域文化とも深く結びついています。志摩市浜島町では、昭和36年(1961年)から続く「伊勢えび祭り」が毎年6月に開催されており、地元の人々や観光客に親しまれています。また、志摩市和具では「伊勢海老刺し網オーナー制度」と呼ばれる取り組みが行われています。参加者が網元となり、漁体験や収穫を楽しむことができます。地域住民と観光客が伊勢エビを通じて交流できる、めずらしいイベントです。
三重県の観光スポット
伊勢エビが楽しめる三重県には、さまざまな観光スポットがあります。今回は、そのなかから特に人気のある3つのスポットを紹介します。
伊勢神宮

「伊勢神宮」は、日本人の総氏神とされる天照大御神をまつる「内宮」と、衣食住の守り神・豊受大御神をまつる「外宮」を中心に、125社を総称する神社です。その歴史は約2000年にわたり、「お伊勢さん」として親しまれています。
入口の宇治橋を渡ると、広大な5500万㎡の神域が広がり、神聖な雰囲気に包まれます。古くから外宮から内宮の順に参拝する風習があり、御朱印も各宮でもらうことができます。格式高い建築様式や別宮、摂社をめぐることで、伊勢神宮の奥深い歴史と文化を体感できます。
おかげ横丁

伊勢神宮内宮の門前町「おはらい町」の中ほどに位置する「おかげ横丁」は、江戸から明治期の伊勢路の町並みを再現した観光スポットです。約4,000坪の敷地に約50の店舗が立ち並び、伊勢ならではのグルメを満喫できます。入口で迎える大きな招き猫や商店の看板猫たちが、人懐こい仕草で和ませてくれます。屋根瓦の装飾も見どころの一つです。
また、「おかげ座 神話の館」では、日本神話の世界を映像と和紙人形で体感できます。毎日がお祭りのような賑やかさと、どこか懐かしいレトロな雰囲気が魅力の「おかげ横丁」は人気の観光スポットです。
なばなの里

「なばなの里」は、三重県にある日本最大級の花と緑のテーマパークです。約30万㎡の広大な敷地には、四季折々の花々が咲き誇り、季節ごとに異なる美しさを楽しめます。特に注目されるのが冬のイルミネーション。プロジェクションマッピングを使わず、LED電球のみで作り上げる光の演出は圧巻で、毎年テーマが変わる大規模な作品はまるで光のアートを体感しているようです。
また、大温室「ベゴニアガーデン」では一年中華やかな花々を鑑賞できます。園内にはレストランや温泉も併設され、家族や友人とゆったりとしたひとときを過ごせる癒しのスポットです。
三重県へのアクセス方法
グルメも観光も魅力的な三重県には、さまざまなアクセス方法があります。日本三大都市でもある東京、大阪、名古屋からも近くアクセスが便利です。
東京からは、新幹線で名古屋まで約1時間40分、名古屋からは近鉄特急またはJRを利用し、伊勢市や松阪方面へ約1時間30分で到着します。飛行機の場合、中部国際空港から電車やバスでアクセス可能です。
大阪からは、近鉄特急が便利で、大阪難波から伊勢市まで約2時間。車の場合は名神高速道路や西名阪自動車道経由で約2時間30分です。
名古屋からは特に近く、近鉄特急や快速みえ号で伊勢市まで約1時間20分、車では東名阪自動車道を利用し約1時間30分です。
車でゆっくりドライブを楽しみながら三重県に向かうのもおすすめです。最適なアクセス方法を探してみてくださいね。
まとめ
伊勢エビはそのおいしさだけでなく、三重県の自然や歴史、地域の人々の努力が詰まった魅力的な食材です。長い歴史を持ち、地域に深く根ざした伊勢エビは、今もなお多くの人々に愛され続けています。
三重県に訪れた際は、ぜひ伊勢エビを味わってみてくださいね。
\ テンポススター加盟店を募集中! /