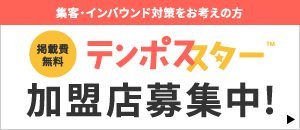ランキング
2024/11/21
元祖スーパーフード『忍者飯』

この記事の目次
忍者とは
忍者は昔から歌舞伎や小説・映画などで人気のテーマでしたが、日本のみならず海外でも子供から大人までよく知られ興味を持たれていますね。
20世紀後半から「Ninja」は特に北米でも映画化されたりその名が広く知れ渡っていたのですが、忍者を題材にしたアニメ「NARUTO」が爆発的な人気を博し、それまでのNinjaのイメージを大きく変えて現代の若者にも浸透していきました。その『NARUTO』の中の忍者はかなり脚色されて…というより全く別物(笑)ですが、では本当の忍者というのどんな人たちだったのでしょうか。
鎌倉時代から江戸時代、特に戦国時代に活躍していた「忍者」は、当時「忍び(Shinobi)]」ほか地方などによって様々な名前で呼ばれていたのですが、昭和30年代の小説などで初めて「忍者」と名付けられたそうです。また、十数年前までは、記録されている古文書もあまり公表されず、学術的にもほとんど研究されていませんでした。ところが2011年三重大学が現代に生きる最後の忍者といわれる伊賀流忍者博物館の名誉会長の川上仁一(Jinichi Kawakami)氏を迎え忍者の講義をして頂いたことから、多くの分野の研究者達によって忍者の研究が始まったのです。
忍者というのは実在した職業であり、大名や藩主などに仕えて報酬を得ていました。その役目はいわゆるスパイ活動と情報操作で、その遂行のために破壊活動や奇襲攻撃はしても戦いが目的ではありません。情報収集によって得たものを細部にわたって記憶し主人に伝えることが役目なので、危機に遭遇しても生き延びて帰らなくてはなりません。敵陣の重要機密をいつどこで手に入れられるかどう忍び込むか調べ踏み込み収集し、見つからず例え見つかって命を狙われても逃げきるということを、その身一つでこなさなければなりません。

それには冷静な判断力と機敏で高い運動能力が必要なのはもちろんのこと、木の板一枚の天井裏や床下のような場所でも音もたてずに身を潜めるのには、喉の渇き・空腹・排泄や眠気を克服し、ちょっと咳き込むどころか少しの音もたてずにじっと相手の様子をうかがうという精神力・忍耐力が求められます。想像を絶する状況ですよね。何かの拍子に傷ついたりかぶれたり、緊張によって起こる腹痛や下痢などにもそれを対処する知識も必要です。
つまり、何事にも動じない精神力・冷静な判断力、ずば抜けて高い運動能力・暗記力を持ち、また器用にどんな人物にもなりすまし敵の目をごまかしたり嘘の情報で敵を惑わせたりする機転や応用力、体調管理のための薬学や、また天文学まで身に着けていたといわれているのが忍者であり、映画の中でなく、ずっと昔この日本に存在していたのです。
忍者の食事
痕跡を残さず侵入するとか水の上を渡ったり水中に潜んだり高い塀をよじ登るための道具を使いこなすことも身に付け、忍術は日ごろから自衛手段として体を鍛えていました。
でも、相当なプレッシャーやストレスに耐えるメンタルや体調をどのようにしてコントロールし、予測できない時間や場所でのエネルギー・栄養補給はどうしていたのでしょう。
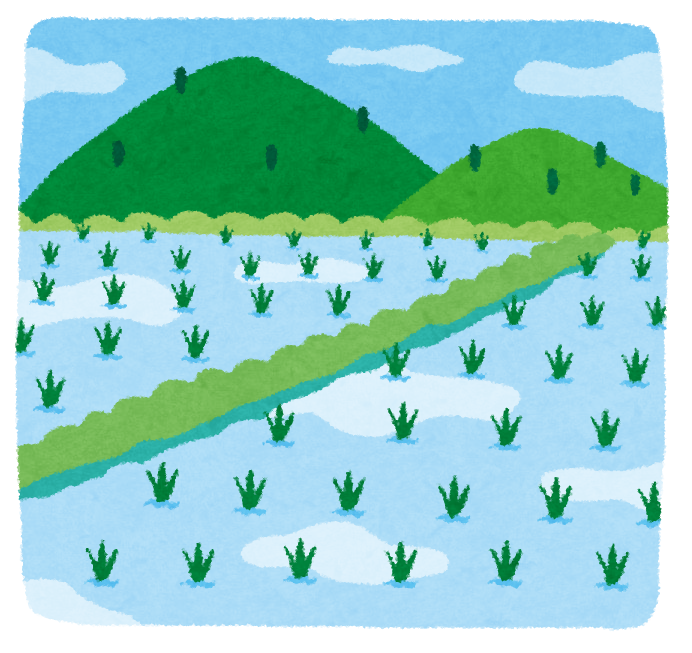
忍者は職業といいましたが、任務に就いていない時は農民として暮らしていました。普段は穀物や野菜など畑で獲れるものを食べていたと言われていますが、ほかにも山菜・野草や、たんぱく質補給のために昆虫・爬虫類・カエルなどの両生類も食べていたようです。その中でも特に大豆や大豆食品の豆腐や味噌、ゴマ・玄米・梅干し・小魚は積極的に食べていたといわれています。粗食でありながらも非常にバランスよく筋肉や体調を考え摂取し任務に備えていました。また、その年の気候や不測の事態で作物が獲れないとか手に入らないときのために備蓄は万全でした。それぞれの食材の長期保存の方法もすべて研究され伝えられてきたのです。いつ任務が命じられても心身共にいい状態でいられるためです。
それでは任務中はというと、まず身の軽さです。高いところによじ登ったり飛び降りたり、敵の攻撃に素早く身をひるがえしたり音もなく超スピードで走ったりするのに身体が重くてはできません。たとえ何日にも及ぶ活動であっても軽装必須なため、せいぜい少量の食糧と敵から身を守る最低限の武器しか携帯できなかったでしょう。肉体を駆使するためには相当のカロリーが必要ですが任務中はどうやって摂取していたのでしょう。

持ち歩きに便利な極小サイズで日持ちし機能的でなくてはならない・・・・そこで考えられたのが忍者飯です。
動物や植物の持っている天然の効能を理解し最大限に取り入れました。最近の研究でも信じられないほどの生薬の種類・量が使われており、その知識の深さや長期保存など多くの知恵が詰まって驚かされたものが、この時代、秘密裏に開発され受け継がれてきたのです。
パワーの源【兵糧丸Hyourougan】
朝鮮人参・ハトムギの種子・ハスの実・うるち米・長芋・シナモンの樹皮などを煎じ氷砂糖液を加え煮詰め、風や熱で繰り返し乾燥させ丸めたものだそうです。うるち米・もち米で練り固めたとも、そば粉やゴマ・黒豆を使ったものなど、地方や味の好みによって異なるそうですが、甘みがあり美味しいといわれています。
この兵糧丸には滋養強壮や疲労回復のほか健康維持を目的とするだけでなく、心を落ち着かせるリラックス効果もあります。またシナモンと糖によりお味もおいしいとのことです。
甲賀忍者おススメ【飢渇丸Kikatsugan】
高麗人参と甘草を酒で煎じて、ユキノシタ・長芋・ハトムギの種子・もち米を加え煎じ一晩おいて団子にしたというもので、朝鮮人参が多いため薬のような匂いであまりおいしくはなかったそうです。しかし「一日三粒飲めば心力衰えることなし」といわれるほど、体に必要なエネルギー源となる炭水化物・脂質・体内のバランスを整えるという効能があり、食というより薬に近いイメージです。
喉の渇きに【水渇丸Suikatsugan】
麦門冬・松の甘皮・茶・柿の葉・桃の葉・ショウガ・ニホンハッカなどレシピは様々ですが、これらに砂糖に少量の水を加え軽く煎じて梅干しの果肉と混ぜ丸めたもので、これを乾燥させて長期保存させるそうです。決め手は梅干しで、この酸味で唾液を分泌させて飲むということです。唾液を飲む‥というのは現代の軍隊でも言われているそうで、全身の水分量を保つという点で、やたら水を飲むよりいいそうです。また咳き込んだりしては潜伏も気づかれてしまいますよね。喉の違和感にも役立ちます。

これらを、任務の時に1個当たり直径2 ~4 cm、重さは20 ~40 gぐらいのものを数個づつ携帯したのではないかと考えられています。
忍者は一日に40里(約160km)走ったとも言われています。そんな身体にこれら携帯食だけでは到底エネルギーが不足してしまうので、潜んでいる時以外は通常の食事をしていたと思われますが、あまり記録に残っていません。
昔から戦国大名たちも、戦には兵力よりも兵の食糧の補給に悩まされたそうです。上杉謙信や武田信玄などはこの『兵糧丸』に価値を見出して活用していたと言われていますが、忍者の存在にしろ、当時の戦の作戦や兵についてはトップシークレットであったため記述はあまり残されていません。

最近あるお菓子のメーカーで「忍者めし」という名前のグミが発売されました。
この兵糧丸がモチーフとなっているそうですが成分は全く違うようです‥ではなぜこの時代に『忍者』というワードが出てきたの?と思われる方もいるかと思いますが、この数年、世界的に起きている問題により、周囲から隔絶して過ごさなければならなかったり、気候変動により今まで食べられたものが簡単に食べられなくなったりもしてます。常日頃から備蓄するということも見習わなくてはなりませんが、ポンと一口で体調も良くしてストレスにも効くスーパーフード、あったら嬉しいですよね!
忍者研究の三重大学でも「「忍者”Ninja”の知恵を活かした人にやさしい循環型社会の構築~文理融合型Ninja研究の成果を世界に発信~」という事業に取り組まれているそうです。
忍者の知恵、もっと知ってみたいですよね!
テンポススターでは下記の体験ツアーをおすすめしています。
執筆者:himiko