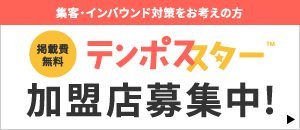ランキング
2024/11/07
日本が誇る伝統楽器『和太鼓』

和太鼓のパフォーマンス、 実際に観たことがありますか?
マーチングバンドなどのドラムとは全く音色が異なるんです。
見た目も”ザ・ニッポン”って感じですよね!
同じ打楽器とはいえ、和太鼓は日本の伝統に基づいた製作方法があるみたいです。

和太鼓には大きさ種類がいろいろとありますが、よく目にするのが【長胴太鼓】、通称【宮太鼓】ではないでしょうか。古くから、祭礼や神社仏閣などでの儀式に使われたことから、そう呼ばれるようになったそうです。
製作方法・素材はメーカーによっても価格によっても異なりますが、最も高価なものは、今ではなかなか手に入らない欅(ケヤキ)が胴に使われています。見た目の良さだけでなく耐久性もよく、なにより音が力強く響きが優れているからです。
その貴重な欅を、少しぷっくりとさせてくり抜いた胴。
このビア樽型こそ、音に深みと重みを持たせるために生み出されたものなんです。ドンッと鼓面を打った時、中の曲面にぶつかった音が重なり合って重厚さが増します。
鼓面には牛革が良いとされています。
なめらかで耐久性のある面を作るのに、米ぬかの酵素で皮の毛穴を開き、毛を削り落としてから乾かしたり水につけたり、厚みを均一にするために0.1ミリ単位で職人さんの手により削られたりと、様々な段階を踏んでようやく胴に付けられる面が出来上がります。(工程には太鼓店によりさまざま)
ここまでの工程を生かすもダメにしてしまうのも、最終段階の面の張りの作業。
薄く仕上げた革の周りに穴をあけ、その穴に短い木の棒を通し、そこにロープをかけて少しずつ伸ばしていきます。上の写真にある『耳』は、飾りの様にも見えますが、実はこの作業の時にできたものだったんです。
長く使った和太鼓の面の張替えも、この作業が行われます。
完璧な鼓面を張り終わってすぐは比較的高い音ですが、時を経るごとに味わい深い音になっていきます。
和太鼓は完成された後、さらに熟成していくんです。
そのためには保管も大切。
作る工程も、人の手に渡ってからも気を緩めませんね!

こうして出来上がった和太鼓から打ち出された音は、緩やかに遠くまで響きわたります。太く重みのある音というのは、空気の振動が細かくないためにスピードはなくても広く届くそう。大きな音でもうるさいと感じないのは、直線的に耳に突き刺さる感じではなく、広がりを持っているからなのでしょうか。
キビキビと、それでいて流れるように打ち鳴らすあのパフォーマンスと、厳粛な重みのある鼓の音色は、今や諸外国のストリートパフォーマンスでも多くの観客を魅了しています。
そんな和太鼓をドーーーンとその手で打ち鳴らしてみたくないですか?
打つこと自体だけでなく、リズムに合わせて数人で共振させる高揚感‼
ドンドコドンッ! ・・・とみんなで揃えて終わる瞬間も、思わず息を飲み、その余韻が広がると共に何だか達成感を得られるんです。
音と遊ぶ!INAKA Experience 和太鼓体験レッスン


執筆者:himiko