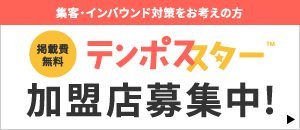ランキング
2024/11/13
【薬膳-YAKUZEN】【瞑想】とは? その①

この記事の目次

先日このコーナーでお勧めした「薬膳料理も楽しめる♪ INAKA Experience 初めての瞑想体験」。
(https://www.tenposstar.com/blog/food-experience/2017/)
薬膳とか瞑想…ってわかっているようで漠然としていて、説明してと言われてもちょっと困ってしまいますよね。
そもそも薬膳とは
『薬膳』からイメージされるのは、辛かったり苦かったり、独特な慣れない香りだったり、その名の通り薬っぽいのかなとイメージしながら『薬膳鍋』など食べてみると案外イケるな…なんて思ったことはありませんか?
「薬」という文字が入っているって、医学と関係あるのでしょうか。
科学的根拠(診察や問診、レントゲンや血液や尿・便などからのデータ)によって、可能性のある疾患を特定して、その疾患に対して薬での治療や手術で切除などを行うのが西洋医学ですね。現代医学ともいい、処方される薬は化学合成によって人工的に作られたものがほとんどで、病気や症状に直接に強く即効性のある効果があります。
問診や聴診器を当てたりお腹や患部に触れてみたりはするのは西洋医学でも用いられてますが、顔色、動作の具合、爪や舌の状態などの観察したり、発音や受け答えを聞くなど、東洋医学は経験に基づいて診断します。
その診断結果に対する治療は、あん摩・指圧・マッサージ・鍼灸という方法のほか、天然由来の漢方薬を用いて自然治癒力を高め本来の健康的な身体に戻していくという、主に中国で発達した古来からの伝統医学なのです。
そして薬膳とは、この東洋医学の飲食療法なのです。食材が持つそれぞれの効能を活かしたお料理であり、添加物や化学調味料は使用されません。

バランスを整える
原因がハッキリした急性期疾患や感染症などには即効性が求められるため東洋医学的な考えは向きませんが、なんとなくダルいなぁ、お医者さんで診てもらっても問題ないのに胃が重いなぁ、台風が来ると頭痛がひどくなるのよねぇ・・なんていう時には、是非薬膳を取り入れてみて下さい!
体の状態と向き合って、どういう効能を持つ食材を摂取すればニュートラルな身体を作れるのか、そこから始まります。
そして、体質を変えるとなってくると、一度食べたら効果が得られるというものではありません。薬膳は続けてみることが大事です。内臓や血液、皮膚・細胞、お肌や髪という私たちの体は摂取したものから作り上げられています。毎日でなくても、頻繁に取り入れてみてください。気付いたら気分までも晴れ晴れ、身も軽くなるり、お肌の状態も良好になると思いますよ!
冬のおすすめ食材
食材にはそれぞれ効能があると前述しましたが、もちろん体を温めるもの・体を冷やすものもあります。それを「五性(または四性)」といい、『寒性・涼性・平性・温性・熱性』という5つに分類されます。寒性が一番身体を冷やすもので、熱性が最もあっためる食材です。
これからの寒い季節には何が良いんでしょう。ちょっと調べてみました。
●野菜
ショウガ・白菜・ネギ・ニラ・小松菜・かぼちゃ・大根・ニンニク・人参・ごぼう・・など
●魚・肉
アジ・サケ・イワシ・ブリ・マグロ・フグ・アナゴ・うなぎ・ムール貝・赤貝・海老・鶏肉・羊肉・豚レバー・・など
●香辛料
棗(なつめ)・シナモン・山椒・唐辛子・胡椒・クローブ(丁子)など
なんだか鍋料理が食べたくなるラインナップですね!寒い地域や季節に収穫されるもの自体、熱の吸収率がいいので、摂取すると体をあたためてくれるんだそうです。
辛い物、特に唐辛子は口に入れるとすぐ汗がにじむような即効性がありますが、ここに挙げたものは代謝を上げることで血行を良くしていくものです。
体が冷える原因には、ストレスや寝不足などで自律神経が乱れたり、ホルモンバランスが崩れたり、血液の流れが滞ってしまったりなどの体の中からのものと、外気が冷えると体の中心に熱をためようと、末端までの血管を収縮して血流を制御し、手足が冷たくなるという環境によるものがあります。
どちらにしても身体が冷えたままでいると、筋肉が硬くなりその硬くなった筋肉を動かそうと関節や骨に負担をかけ痛みを感じるようになります。我慢すれば大丈夫などと身体の冷えを見逃さず、温めるようにしましょう。
また、体温を上げることによって免疫力も高まります。冬はとても乾燥しウィルス感染もしやすくなりますので、食物からも免疫力アップをお勧めします。

これから年明けにかけ、お酒を飲む機会が増える季節。二日酔いにおすすめの食材は、シジミ・帆立・柿・トマト・大根などだそうです。最近柿を使ったレシピをよく目にするようになりました。ぜひ試してみてはいかがですか☺
執筆者:himiko