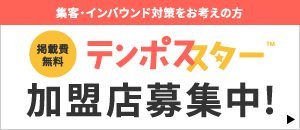ランキング
2024/12/30
岐阜県のご当地B級グルメ「朴葉味噌」とは?特徴や歴史を紹介!

この記事の目次
朴葉味噌は、岐阜県飛騨地方を代表する郷土料理です。乾燥した朴の葉の上に味噌をのせ、囲炉裏でじっくり焼き上げることで、香ばしい香りと奥深い味わいを楽しめます。その独特の風味は、飛騨地方を訪れる観光客にも人気があります。
そんな朴葉味噌の特徴や歴史について探っていきましょう。
朴葉味噌の特徴

朴葉味噌に使われるのは、飛騨地方特有の麹味噌です。塩気が控えめで甘みが強いのが特徴で、多くのお店では砂糖、みりん、酒、生姜などを加えて味付けし、より深みのある甘さに仕上げています。この味噌を朴の葉に広げて焼くと、葉が焦げる際に生まれる香ばしい香りが加わり、風味が一層豊かになります。
また、ネギやきのこを加えるのが一般的で、シンプルながらも奥深い味わいを堪能できます。炊きたてのご飯との相性は抜群で、香ばしい香りと味噌の甘みがご飯の自然な甘さを引き立て、「何杯でもおかわりできる」と評されるほど。また、味噌そのものが濃厚なため、ほかのおかずがなくても十分に満足感を得られます。
さらに、飛騨地方が誇るブランド牛「飛騨牛」の薄切りをのせた朴葉味噌も人気の一品です。飛騨牛の上質な脂が味噌に溶け込むことで、濃厚な旨みが生まれ、贅沢感を味わうことができます。朴葉味噌は、ご飯のお供としてはもちろん、お酒のあてとしても愛されています。
朴葉味噌の「朴葉」とは?

朴葉味噌に欠かせない「朴葉」は、ホオノキ(朴の木)の葉を指します。ホオノキはモクレン科の落葉高木で、日本各地の山林に自生しています。その葉は30〜40cmと非常に大きく、撥水性に優れているため、具材を乗せやすく、焼いたり混ぜ合わせたりしてもへたることがありません。
朴葉は独特の香りを持ち、焼くことでその香りが味噌や具材に移り、料理全体に深みのある風味を生み出します。また、抗菌・殺菌作用があり、古くから食品を包んで保存するためにも利用されてきました。実際、「朴葉」という名前は「包む」という意味の言葉に由来するという説もあり、朴葉味噌の調理法とも深い結びつきがあります。
飛騨高山地方の山林には多くのホオノキが自生しており、梅雨ごろには白く大きな花を咲かせます。晩秋になると霜の降りはじめとともにホオノキは葉を落とします。この時期に拾い集められた茶色い葉は、3日ほど塩水に浸したあと陰干しをして保存され、朴葉味噌に使用されます。
朴葉は単なる調理器具ではなく、料理に香りと風味を与え、抗菌性で保存性を高めるなど、朴葉味噌の味と伝統を支える重要な存在です。この葉なくしては、朴葉味噌の魅力を語ることはできません。
朴葉味噌の歴史
朴葉味噌の歴史には諸説ありますが、その発祥は岐阜県飛騨地方の厳しい冬に深く根付いています。この地域の冬は非常に寒く、漬物樽のなかの漬物が凍るほどでした。そんななか、囲炉裏の火に朴葉を敷き、その上で凍った漬物を温め、味噌を加えて食べたことが朴葉味噌の始まりとされています。
もう一つ有力な説として、林業が盛んな飛騨地域で働く杣人(そまびと)たちの知恵があります。山で食事をする際、周囲に生えているホオノキの葉を皿代わりに使い、焼き味噌を作っていたことが朴葉味噌の原型となったと言われています。
朴葉味噌は、こうした山間部の生活に根付いた知恵から生まれ、時代とともに一般家庭へと広がっていきました。昭和40年(1965年)代には土産物として販売されるようになり、飛騨地方を代表する郷土料理として全国的に知られるようになります。そして、平成19年(2007年)には農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に選定され、その存在はさらに広く知られることとなりました。
香ばしい香りと奥深い味わいを持つ朴葉味噌は、飛騨の食文化を象徴する一品として、現在でも多くの人々に愛され続けています。
岐阜県の観光スポット
朴葉味噌が楽しめる岐阜県には、さまざまな観光スポットがあります。今回は、そのなかから特に人気のある3つのスポットを紹介します。
岐阜城

「岐阜城」は、岐阜市のシンボルとして知られる歴史深い山城です。金華山の山頂に位置し、その堅固な立地から「難攻不落の城」と呼ばれてきました。もともとは斎藤道三の居城「稲葉山城」として築かれ、戦国時代には織田信長がこの城を攻略し、城名と地名を「岐阜」と改めたことで知られています。天下統一を目指した信長が拠点とした岐阜城は、「美濃を制する者は天下を制す」と言われるほど重要な地でしたが、関ヶ原の戦いを前に落城。その後、廃城となりました。
現在の城は昭和31年(1956年)に復興され、内部は資料展示室や展望台として整備されています。展望台からは岐阜市内を一望でき、夜間営業時には美しい夜景も楽しめます。信長ゆかりの史跡や戦国時代の石垣も見どころの一つです。
飛騨高山の古い町並

飛騨高山の「古い町並」は、江戸時代の城下町や商人町として発展した高山市の中心に位置し、国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。特に、上三之町、上二之町、上一之町周辺の「三町通り」は、趣深い町家建築が立ち並ぶ散策スポットとして人気を集めています。
通り沿いには、飛騨牛グルメやみたらし団子を提供するお店が軒を連ね、食べ歩きを楽しむことができます。また、一角にある「まちの体験交流館」では、伝統工芸の制作体験も可能です。さらに、近隣には日本唯一現存する郡代役所「高山陣屋」があり、江戸幕府の歴史を感じられる貴重なスポットとなっています。飛騨高山の「古い町並」は、歴史と文化、美食を楽しみたい方にぴったりの観光地です。
白川郷合掌造り集落

「白川郷合掌造り集落」は、日本有数の豪雪地帯に位置する全国最大規模の合掌集落で、平成7年(1995年)に世界文化遺産に登録されました。数百年の歴史を持つ合掌造りの家屋が100棟以上現存し、現在も住民が暮らす「生きた集落」としてその姿を保っています。和田家や長瀬家などの大規模な合掌造り民家は内部見学が可能で、5階建ての建物では屋根の構造を間近で見学でき、当時の暮らしの知恵に触れることができます。
白川郷では、四季折々の美しい風景を楽しむことができます。春夏には緑豊かな田園風景、秋には鮮やかな紅葉、冬には雪化粧に覆われた幻想的な景色が広がります。特に1月中旬から2月上旬に行われるライトアップイベントは、多くの観光客に人気です。
岐阜県へのアクセス方法
グルメも観光も魅力的な岐阜県には、さまざまなアクセス方法があります。日本三大都市でもある東京、大阪、名古屋からのアクセスも便利です。
東京からは新幹線で名古屋駅まで約1時間40分、その後JR東海道本線または特急「ひだ」を利用して岐阜駅へ約20〜30分で到着します。また、高速バスを利用すれば約7〜8時間で岐阜市内へ直行することができます。
大阪からは、新大阪駅から新幹線「のぞみ」で名古屋駅まで約50分、その後JR東海道本線の新快速で約20分です。また、高速バスなら約6時間で到着します。
名古屋からは最も近く、JR東海道本線で岐阜駅まで約20分。特急「ひだ」や高速バスも利用でき、観光地である飛騨高山や白川郷方面へのアクセスも便利です。
車でゆっくりドライブを楽しみながら岐阜県に向かうのもおすすめです。最適なアクセス方法を探してみてくださいね。
岐阜県の位置
-947x1024.jpg)
まとめ
朴葉味噌は、飛騨地方の厳しい自然と生活の知恵から生まれた郷土料理です。その香ばしい香りと深い味わいは、ご飯との相性が抜群で、心をほっと和ませてくれます。
飛騨を訪れた際は、ぜひ朴葉味噌を味わってみてくださいね。
\ テンポススター加盟店を募集中! /