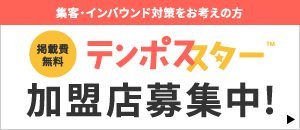ランキング
2025/01/02
京都府のご当地B級グルメ「宇治金時」とは?特徴や歴史を紹介!

この記事の目次
宇治金時は、かき氷に抹茶シロップと小倉あんをかけた日本らしい氷菓子です。夏の風物詩として人気があり、老若男女問わず愛されています。
そんな宇治金時の特徴や歴史について探っていきましょう。
宇治金時の特徴
宇治金時の抹茶シロップには、「宇治茶」が使用されており、深い香りと上品な甘さを楽しむことができます。白玉やアイスクリーム、抹茶ゼリーをトッピングしたパフェ風のアレンジも人気で、甘すぎない上品な味わいが暑い季節にぴったりの一品として親しまれています。
名前の由来は「宇治」と「金時」を組み合わせたものです。「宇治」は京都府宇治市で生産される高品質な茶葉「宇治茶」にちなみ、抹茶を連想させることから名付けられました。「金時」は、平安時代後期の武士で童話「金太郎」のモデルとなった坂田金時に由来します。その赤い肌が小豆を連想させることから、餡や小豆の代名詞として使われるようになったと言われています。
全国的に宇治金時を提供する飲食店が増えていますが、京都産の宇治茶が使用されているとは限りません。本場の宇治金時を楽しむなら、京都を訪れるのがおすすめです。特に宇治市内の茶屋や道の駅では、宇治茶を使った本格的な抹茶シロップで作られる宇治金時が堪能できます。また、宇治茶専門店では抹茶シロップが販売されているため、お土産にもぴったりです。
宇治金時に使われる宇治茶とは?

宇治茶は、日本を代表する高級茶の一つです。京都、滋賀、奈良、三重で摘み取られた茶葉を、京都府内で加工・仕上げたものが「宇治茶」と呼ばれます。その本場とされるのは、宇治市や和束町、南山城村など、京都府南部の山城地域です。
宇治茶は栽培や製造方法によって種類が分かれます。露天で栽培した新芽を蒸して揉む「煎茶」、新芽を覆いで直射日光から守りながら栽培する「玉露」、玉露のように栽培されつつ蒸した葉を揉まずに作る「甜茶」、甜茶を粉末にした「抹茶」などがあります。宇治茶は飲み物として楽しむだけでなく、菓子や料理の素材としても広く利用されており、京都の名物として観光客に人気です。
宇治茶の起源は建久3年(1191年)、栄西禅師が宋から持ち帰った茶の種子を、明恵上人が京都市右京区の栂尾の地に植えたことに始まるとされています。その後、足利義満や義政の時代に栽培が奨励され、宇治市周辺に茶園が広がり、一級品として高い評価を受けました。さらに、茶道の発展とともに大衆にも親しまれるようになりました。
江戸時代中期には、永谷宗圓によって「宇治製法」が確立されました。蒸した茶の新芽を焙炉で揉みながら乾燥させるこの製法により、宇治茶の品質がさらに高まりました。その結果、宇治茶は全国にその名を知られるようになりました。
宇治金時の歴史

宇治金時の発祥には諸説あります。そのなかでも有名なのは、江戸時代、戦国武将がきび砂糖と抹茶をかけた「宇治氷」を作り、甘いもの好きだった徳川家康が餡を加えたことで、宇治金時が生まれたという説です。
ちなみに、かき氷そのものは平安時代には「削り氷(けずりひ)」として楽しまれていました。清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』には、削った氷に甘味料をかけて食べる場面が描かれており、当時の貴族にとって特別な冷菓だったことがわかります。冷蔵庫や製氷機のない時代、氷は非常に貴重なものでした。冬に切り出した天然の氷を「氷室(ひむろ)」に保存し、夏に利用する方法が取られていました。
奈良時代には天皇への献上品として氷が使われていた記録もあり、江戸時代には加賀藩が氷を将軍に献上したことが知られています。運ぶ間に溶けて小さくなった氷を小刀で削り、宮中で楽しんでいたとされます。当時、こうした氷を味わえたのは限られた貴族階級だけでしたが、その後、冷蔵技術が発達すると氷は広く普及し、かき氷は一般の人々にも親しまれる夏の定番スイーツとなりました。
京都府宇治市の観光スポット
宇治金時が楽しめる京都府宇治市には、さまざまな観光スポットがあります。今回は、そのなかから特に人気のある3つのスポットを紹介します。
平等院

「平等院」は、世界遺産「古都京都の文化財」の1つで、10円玉に描かれた「鳳凰堂」で知られています。平安時代、藤原道長の別荘を息子の頼通が永承7年(1052年)に寺院へ改め、極楽浄土の宮殿を再現する思想で創建されました。最大の見どころである鳳凰堂(国宝)は、池に浮かぶような優雅な佇まいが特徴で、屋根には金色に輝く鳳凰が飾られています。
平成6年(1994年)に世界遺産に登録され、平成13年(2001年)には博物館「鳳翔館」が開館。庭園や貴重な文化財を楽しむことができます。また、平成25年(2014年)の改修を経て、創建当時の姿に近づいたとされています。さらに、境内には日本茶専門店「茶房 藤花」があり、宇治茶を使った特別な抹茶を味わうこともできます。
宇治橋

「宇治橋」は、大化2年(646年)、奈良元興寺の僧・道登によって架けられたと伝えられる「日本三古橋」の一つです。瀬田唐橋、山崎橋と並び、日本の歴史を象徴する由緒ある橋として知られています。現在の宇治橋は平成8年(1996年)に架け替えられたもので、檜製の高欄や青銅製の擬宝珠を備え、歴史的な趣を残したデザインが特徴です。
橋の上流側に張り出す「三の間」は、守護神・橋姫を祀った名残や、豊臣秀吉が茶の湯に使う水を汲ませた場所とされる伝説の地で、宇治の茶まつり「名水汲み上げの儀」が行われるなど、地域の文化とも深く結びついています。また、宇治橋からは宇治川の美しい景色を望むことができ、春には川沿いに咲き誇る約2,000本の桜が訪れる人々を魅了します。
宇治市源氏物語ミュージアム

「宇治市源氏物語ミュージアム」は、1000年以上にわたり読み継がれてきた不朽の古典文学『源氏物語』をテーマにした専門博物館です。『源氏物語』の主要な舞台となった宇治を訪れるなら、ぜひ立ち寄りたいスポット。平成10年(1998年)に開館し、光源氏や「宇治十帖」の世界を模型や映像でわかりやすく紹介しています。
館内では、平安時代の調度品や六条院の縮小模型、実物大の牛車のレプリカが展示されており、当時の華やかな文化を体感できます。また、3000冊以上の蔵書が揃っており、文章を通じて『源氏物語』の魅力を楽しむこともできます。定期的に開催される講座やイベントでは、物語や平安文化について深く学ぶことができます。紫式部が描いた平安時代の世界に思いを馳せながら、『源氏物語』の奥深い魅力を堪能できる人気のミュージアムです。
京都府宇治市へのアクセス方法
グルメも観光も魅力的な京都府宇治市には、さまざまなアクセス方法があります。日本三大都市でもある東京、大阪、名古屋からのアクセスも便利です。
東京からは、東海道新幹線を利用して京都駅まで約2時間。京都駅からはJR奈良線に乗り換え、宇治駅まで約20分で到着します。
大阪からは、JR大阪駅から大阪環状線とJR奈良線を乗り継ぎ、宇治駅まで約1時間。京阪電車を利用する場合は、淀屋橋駅から京阪本線で中書島駅へ行き、京阪宇治線に乗り換えて宇治駅まで約1時間です。
名古屋からは、東海道新幹線で京都駅まで約40分。京都駅からJR奈良線に乗り換え、宇治駅まで約20分で到着します。
車でゆっくりドライブを楽しみながら宇治市に向かうのもおすすめです。最適なアクセス方法を探してみてくださいね。
まとめ
宇治茶の深い香りと上品な甘さ、かき氷の爽やかさ、小倉あんの甘みが調和した宇治金時は、日本の伝統的な味わいと夏の涼を感じさせる一品です。暑い夏にぴったりの宇治金時は、その歴史や背景を知るとさらに味わい深く感じられます。
京都府を訪れた際は、ぜひ本場の宇治金時を味わってみてくださいね。
\ テンポススター加盟店を募集中! /