ランキング
2025/02/24
奈良(奈良エリア)でやるべき10のこと

この記事の目次
「奈良(奈良エリア)でやるべき10のこと」をご紹介します。
東大寺

奈良県奈良市に位置し、聖武天皇により745年に国家の安定と平和を祈願する目的で創建されました。日本を代表する仏教寺院で華厳宗の大本山です。1998年に「東大寺」はユネスコ世界文化遺産になりました。「大仏」は奈良の象徴であり、高さ約14.7メートル、重さは250トン以上とされています。圧倒的な存在感の大仏はファンも多く多くの人が訪れます。
奈良公園

1880年に開設された、日本でも有数の歴史ある都市公園です。1300頭を超える鹿が暮らしており、園内どこでも出会えます。野生動物で、天然記念物の「鹿」は奈良時代に春日大社が創建された際、ご祭神が白鹿に乗ってやってきたという言い伝えから春日の神さまのお使いとして大切に保護されてきました。鹿せんべいをあげることも出来ます。
浮見堂

1916年に旧浮見堂が建てられました。その後、老朽化し現在の「浮見堂」は再建されています。座って景色を眺めたり休んだりすることができます。浮見堂は鷺池の水面に写る姿が絵になります。春に桜、夏に百日紅(サルスベリ)、秋に紅葉、冬に雪と四季折々の景色が美しく、楽しむことができ、ライトアップも通年で見る事が出来ます。貸しボートに乗ることもできます。
元興寺

718年に平城遷都にともない、飛鳥の地にあった日本初の本格的寺院、法興寺(ほうこうじ)が平城京に移され、名前を「元興寺」としたのが始まりとされています。「五重小塔」「智光曼荼羅」などの多くの建造物や仏像は国宝・重要文化財になっています。「元興寺極楽堂」は日本最古の屋根瓦が今も使われており歴史があります。
薬師寺

680年に天武天皇が皇后の病気平癒を祈願して創建された寺院です。718年に現在の地になりました。「東塔」と「東院堂」は国宝に指定されています。「東塔」は創建時のまま唯一現存する建物で六重の塔に見えますが実際には三重の塔です。「東院堂」は日本最古の禅堂といわれており歴史があります。
平城宮跡

710年に藤原京より都を移された平城京の中心であった「平城宮」の宮跡です。1998年には世界遺産に登録されています。「第一次大極殿」は天皇の即位式などの儀式が行われた建物です。「朱雀門ひろば」には展望デッキ、レンタサイクル、レストランなどもあります。

夜のライトアップで見る「平城宮」も幻想的です。
春日大社

社伝では768年とされていますが、実際には奈良時代の初めにさかのぼるとされています。古くから神の降臨する山として神聖されていた春日山・御蓋山に四柱の神々を祀り創建されました。平城京の鎮護日本の国の繁栄と国民の幸せを願意をこめて作られた全国に3000近くあるといわれている春日神社の総本社です。「本殿」は鮮やかな朱色が目を惹き綺麗です。

「灯籠」は平安時代(794〜1180年)から現在までに奉納されおよそ三千基あります。苔と灯籠が相まりとても綺麗でフォトジェニックです。
興福寺

669年藤原鎌足の妻である鏡女王が夫の病気平癒を願って建立した山階寺を創建しました。その後、710年平城京への遷都の際に現在の奈良の地に移され「興福寺」になったそうです。多くの国宝や重要文化財があります。「五重塔」は日本で二番目に高い木造の塔です。大規模な保存修理工事の為、見れるようになるのは2031年の予定です。
正倉院

756年に聖武天皇の七七忌法要の際、聖武天皇を祈願しゆかりの品々600数十点、薬物60種を大仏に奉納し、それを保存する宝庫として建立したのが「正倉院」です。校倉造は国宝に指定されています。北倉・中倉・南倉の3つに区分されており、高床式の2階建てになっています。約9000点もの宝物は世界的に知られた古美術の宝庫で年に一回の秋にその中の一部を展示する「正倉院展」が行われます。
氷室神社

710年に御蓋山の西麓に創建され、860年に現在の場所になったと伝えられています。かき氷を奉納する「献氷参拝」があり珍しいです。かき氷をお供えしてお賽銭を入れて拝礼したあと、そのかき氷を食べることができます。6月中旬から9月中旬頃までの期間限定です。

鏡池のほとりにある「しだれ桜」は奈良で最も早く咲く桜として有名です。その他にもソメイヨシノも咲き綺麗です。
まとめ

「奈良(奈良エリア)でやるべき10のこと」をご紹介しました。歴史的な観光地が多くフォトジェニックな場所ばかりです。「東大寺」の大仏は有名で存在感があります。「奈良公園」では鹿と戯れる事が出来ます。「氷室神社」ではかき氷を食べる事ができとても珍しい体験ができます。是非訪れてください。







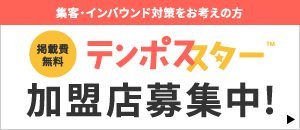





でやるべき10のこと1-e1741139482232.jpg)
