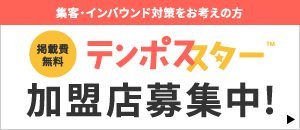ランキング
2023/11/05
【まとめ】日本各地のご当地うどんを一挙ご紹介!

この記事の目次
のどごしやさまざまな食感が楽しめる「うどん」。麺の太さやつゆとの相性、トッピングなど、日本の地域ごとに個性豊かなうどんがあります。
この記事では全国各地のご当地うどんをご紹介します。その味わいや特徴など、ご当地ならではの名物うどんの魅力に迫ります。
日本のご当地うどんとその特徴
ここからは、日本のご当地うどんやその特徴についてご紹介します。
豪雪うどん 北海道
豪雪うどんは北海道のニセコ、倶知安町(くっちゃんちょう)の中心部にあるホテルのお店で食べられます。しなやかなコシと透明感のある白い麺が特徴です。
倶知安町特産の男爵いもを使ったうどんで、噛んだときの弾力とつるんとしたのど越し、後味の軽やかさにもぜひ注目してみてくださいね。
稲庭うどん 秋田県
なめらかな舌ざわりとつるつるとしたのどごしの稲庭うどんは、約350年もの歴史をもつ秋田の名物うどんです。食べた瞬間、つるりとしたなめらかさで、少し細くて平たい麺にもしっかりとしたコシがあります。
3〜4日間をかけて熟成させることで、コシの強さを引き出しているそうです。
あんかけうどん 岩手県
岩手県の中南部江刺(えさし)地区で、昭和初期から冬のごちそうとして食べられていた、あんかけうどん。和風だしの効いたしょうゆベースのあんかけを、ゆでたうどんにかけていただきます。
しいたけやかまぼこ、卵などをトッピングし、季節にかかわらず食べられる、懐かしのご当地うどんになっています。
ひっぱりうどん 山形県
ゆでた鍋から直接うどんをひっぱるようにしていただく、ひっぱりうどん。山形県の村山市戸沢地区では、寒い時期に保存食の乾麺や缶詰、納豆などを持ち寄って、特製のつけダレにからめて食べたのが、ぴっぱりうどんのはじまりだと言われています。
つけダレは納豆やさば缶、ねぎ、しょうゆなどを混ぜたもので、自由にアレンジできるのも特徴です。
耳うどん 栃木県
栃木県佐野市千波に伝わるご当地うどんです。耳の形に似ていることからこの名前がついたそう。
年の暮れに作って正月に食べるのが習慣になっていて、年の初めに耳を食べることで、1年を通して悪いことを聞かず、よい年になりますようにといった願いが込められています。
水沢うどん 群馬県
つるっとしたコシと透明感のあるつやが特徴の水沢うどん。群馬県渋川市の名物で、麺の太さはやや太め。安土桃山時代に湯治客や参拝者に向けて、地元の小麦や水沢の湧水を使ってうどんを提供するようになったのが、はじまりだと言われています。
こだわりの小麦と水、塩のみを使って作られるそのおいしさは、なんと400年以上もの歴史があるのだとか。
ひもかわうどん 群馬県
群馬の桐生地方に伝わる幅広の麺です。お店によっては10cm以上のものまで、その幅はさまざま。その分非常に薄く、つるりとしたなめらかなのどごしと見た目に反した強いコシが特徴です。きれいに折りたたまれた形で提供され、つけ汁につけていただきます。
館林うどん 群馬県
豊かな小麦の風味に加えて、つやとなめらかさがある館林うどん。赤城山の伏流水が流れる館林市は「水のまち」でもあり、良質な小麦がとれることから昔からうどんを作って食べる文化がありました。
邑楽館林(おうらたてばやし)の小麦「百年小麦」を使うのが特徴で、麺のみずみずしさをストレートに味わえる釜玉うどんが名物になっています。
武蔵野うどん 東京都・埼玉県
コシのある太麺から力強さを感じる、武蔵野うどん。東京都の多摩地域と埼玉の西部に伝わるうどんです。かつお風味の温かいしょうゆだしにお肉を入れて、糧(かて)と呼ばれるゆでた野菜を冷たいうどんにからませて食べるのが特徴です。
加須うどん 埼玉県
加須うどんは約300年前に、利根川の船の発着所や市内にある總願寺(そうがんじ)で参拝客にうどんを作ってもてなしたのが、はじまりだと言われています。足踏み」や「寝かせ」といった手打ちうどんならではの工程を繰り返すことで、麺に強いコシとのどごしのよさがうまれます。
熊谷うどん 埼玉県
熊谷うどんは熊谷産の小麦を50%以上使い、地元で製麺されたうどんです。小麦は「さとのそら」や「あやひかり」、「農林61号」などの小麦があり、「さとのそら」は時間がたってものびにくく、「あやひかり」は弾力があってなめらかな食感のうどんに。
そして、「農林61号」は風味がよく、ほどよい硬さでつゆがしみこみやすいなど、それぞれの小麦によって少し違いがあります。
冷汁うどん 埼玉県
埼玉県の冷や汁うどんは、忙しい農作業の合間にとれる食事として重宝されています。たんぱく質や塩分がとれるみそを使い、きゅうりや大葉、みょうがなどの野菜を加えることで、暑い日にもさっぱりと食べられる農家の定番食になっています。
吉田のうどん 山梨県
吉田のうどんはびっくりするような強いコシと歯ごたえ、しっかりとした太さのある麺が特徴です。みそやしょうゆベースのだし汁でいただく、吉田市周辺の郷土料理でもあります。
冷水で冷やしたあとに、煮干しやかつお節でとっただし汁やみそ、しょうゆを入れて、蒸したキャベツ、甘辛く煮た馬肉をのせて食べることもあります。
氷見うどん 富山県
氷見(ひみ)うどんは、富山県氷見市の郷土料理。油を使わず何度も手で引き伸ばすようにして作られる手延べの製法で、細めながらも独特の強いコシとお餅のような歯ごたえ、のどごしのよさがあります。ざるや釜揚げ、かけうどんにしても食べられます。
味噌煮込みうどん 愛知県
八丁味噌仕立てのコク深いつゆに、コシのあるうどんを入れて煮込んだ、味噌煮込みうどん。塩を使わず、小麦粉と水のみで作られた麺は煮込んでものびにくいのが特徴です。
土鍋に入れて作るので、保温性が高く、あつあつの状態で食べられ、はじめと終わりでうどんの食感が変わるのも、味噌煮込みうどんの醍醐味なんですよ。
伊勢うどん 三重県
太くてやわらかい麺に、たまり醤油をベースにした濃い色のつゆが伊勢うどんの特徴です。塩味が強いと思われがちですが、かつおの風味などが感じられ、角の立たない味わいになっています。
伊勢市民のソウルフードでもあり、スーパーなどで気軽に購入できる讃岐うどん。一般的なうどんよりかなり太いので、市販の麺はゆでた麺で売られているのも特徴です。
かすうどん 大阪府
かすうどんは、大阪の南河内地域で食べられてきた郷土料理です。「かす」は牛の小腸(ホルモン)を揚げて余分な水分を飛ばしたもので、「油かす」とも呼ばれます。外はカリカリと香ばしく、中はぷるっとした独特の歯ごたえが特徴です。凝縮されたかすの旨みがつゆに広がり、味わいにぐっと深みが増しますよ。
ホルモン焼きうどん 兵庫県
兵庫県の佐用市で生まれた、ホルモン焼きうどん。鉄板でホルモンや野菜、うどんを焼いて特製のつけダレにいただく鉄板料理です。かつて畜産業や精肉業が盛んだった佐用市で手に入りやすかったホルモンと野菜を、うどんと一緒に焼いて食べるようになったのが、ホルモン焼きうどんのはじまりだと言われています。
梅うどん 和歌山県
紀州南高梅の完熟した梅肉を練り込んで作る、梅うどん。淡いピンク色の麺はゆでるとふんわりと梅の香りが広がり、酸味はないやさしい味わいのうどんに仕上がっています。しっかりとしたコシとなめらかな食感が特徴で、青じそや梅干し、わかめ、かつお節、かまぼこなどをのせていただきます。
津山ホルモンうどん 岡山県
さまざまな部位のホルモンに、みそやしょうゆ味のタレをからめて焼き上げる、津山ホルモンうどん。津山のホルモンは臭みがなく、今も精肉業が盛んなことから新鮮なホルモンが手に入る地域としても有名です。お好みでゆずの果汁を絞っていただくのもおすすめですよ。
鳴門うどん 徳島県
細めでやわらかく、ふぞろいな麺が特徴の鳴門うどん。別名「鳴ちゅるうどん」とも呼ばれます。煮干しのあっさりとしただしと、刻み揚げやねぎのシンプルなトッピングで、飽きの来ないやさしい味わいが鳴門うどんの魅力です。
かつて塩田地帯として栄えた鳴門市で、仕事の合間に食べる手軽な食事として好まれていたそうですよ。
細うどん 広島県
海で働く人々が限られた時間で「早く、おいしく食べられるように」と、3〜4mmほどの細麺にして提供するようになったのが、広島県呉市の細うどん。やわらかい食感でつゆがよくからむようになっています。
大きめの天ぷらや甘辛いお肉、ねぎなど、具だくさんでささっと食べられる細うどんは、地元で今も愛されています。
讃岐うどん 香川県
もちもちの食感とつるっとしたのどごしの讃岐うどん。「足踏み」という製法で作られた麺は、足で踏むことで弾力とコシのあるうどんになります。かけうどんやぶっかけうどん、ざるうどん、釜揚げうどんなどさまざまな食べ方がある中で、ぶっかけうどんはもっとも定番な食べ方。
ねぎや天かす、大根おろしをのせてもおいしいですよ。
博多うどん 福岡県
博多のうどんはコシが少なく、麺がやわらかいのが特徴です。いりこをベースにした薄口で甘めのつゆをかけていただきます。やさしい味わいで昼食や小腹がすいたときの食事、お酒を飲んだ後のしめにも食べられます。
博多うどんのトッピングはごぼうを揚げた「ごぼ天」や丸い形の天ぷらの「丸天」など、ほかの地域にはないものがありますよ。
五島うどん 長崎県
五島うどんは、棒状の生地を2本の箸にかけながら引き延ばして束ね、ひも状の細い麺にしていきます。麺の細さに負けない強いコシとのどごしのよさが特徴です。島の特産品である椿油を塗ることで麺がのびにくく、コシの強さにもつながるのだそう。
あご(飛魚)を炭火で焼いて乾燥させた焼きあごを使っただしは、五島うどんと相性ぴったりです。
魚うどん 宮崎県
魚うどんは漁業の街、日南市の郷土料理です。戦中戦後の食料が少なかった時代に、たくさんとれる魚を使って作られたのが魚うどんです。もともとは魚のすり身だけで作られていましたが、最近では魚のすり身に卵、塩、少量の片栗粉や小麦粉が入ることも。
うどんから魚の旨みが出るので、ゆで汁に醤油を少しかけるだけで味わい深いつゆになります。
まとめ
今回は全国各地のご当地うどんをご紹介しました。それぞれの地域で特色のあるうどんが多く、トッピングやつゆの違いもバリエーション豊か。
ぜひ旅行先や出張先などで、その土地でしか味わえないご当地うどんを味わってみてはいかがでしょうか?
\ テンポススター加盟店を募集中! /