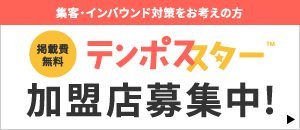ランキング
2025/02/04
日本のお花見文化とは?歴史や楽しみ方を紹介

この記事の目次
日本の春のシンボルといえばお花見。桜を眺めながら楽しむお花見は、春の行楽の定番です。親しい人たちと集まり、桜の木の下でお酒を飲んだり談笑したりする光景は、春の風物詩として日本各地で親しまれています。
しかし、海外では外での飲酒を制限する法律が多いため、桜の下で宴会をする習慣は広まっていません。そのため、お花見の歴史や楽しみ方をくわしく知る方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、お花見の歴史や楽しみ方などをご紹介します。美しい桜をさらに深く楽しめるようになりますよ。
日本のお花見文化の歴史
お花見は日本特有の文化です。南北に長い日本では、地域ごとに桜の開花時期が異なるため、長い期間楽しめるのが特徴です。また、日本人は自然と共生する文化を大切にし、桜の儚い美しさを愛でる習慣を育んできました。
さらに、冷めてもおいしい料理が花見弁当に適していることや、日本では外での飲食が一般的であることも、お花見文化を支える理由の一つです。
そんな日本の春を象徴する「お花見」ですが、実はその歴史は意外と古く、桜ではなく梅から始まったといわれています。お花見がどのようにして現在の形に発展したのか、その歴史を探ってみましょう。
お花見の起源 – 奈良時代の「梅花の宴」

お花見の起源は奈良時代(710〜794年)にさかのぼります。当時、花見の対象は桜ではなく「梅」でした。中国から伝わった梅の花は、香りや色の美しさで貴族に愛され、『万葉集』には梅を詠んだ歌が110首も収められています。奈良時代の代表的な花見イベントが「梅花の宴」です。
「梅花の宴」とは、庭に咲く梅を眺めながら詩を詠む優雅な集まりで、現代のお花見とは少し違い、静かに自然を楽しむものでした。このように、奈良時代のお花見は、季節の移ろいを愛でる貴族の伝統行事として行われていました。
平安時代 – 桜が花見の主役に

平安時代(794〜1185年)になると、花見の主役は梅から桜へと移りました。これは中国文化の影響が薄れ、日本独自の「国風文化」が発展したことによると考えられています。桜の華やかさと儚さは、当時の日本人の美意識に深く響いたのです。
812年、嵯峨天皇が京都の庭園「神泉苑」で行った「花宴の節」は、日本で記録に残る最古のお花見とされています。また、宮中には「左近の桜」と呼ばれる桜の木が植えられ、貴族たちはその下で詩を詠みながら春の訪れを楽しんでいました。平安時代の文学作品、『源氏物語』にも桜を愛でる場面が数多く描かれており、この時代にはすでに桜が特別な存在であったことがわかります。
鎌倉・室町時代 – 武士に広がるお花見

鎌倉時代(1185〜1333年)から室町時代(1336〜1573年)にかけて、お花見は武士の間にも広がりました。武士たちは桜を眺めながら宴会を開き、戦乱の合間に束の間の安らぎを楽しんでいたのです。
特に室町時代には、京都の「吉野」や「醍醐」など、桜の名所を訪れることが流行しました。このころのお花見は、桜を愛でるだけでなく、貴族や武士たちが集まり交流する格式高い社交の場でもありました。
江戸時代 – 庶民に広がる桜文化

江戸時代(1603〜1868年)になると、お花見は武士や貴族だけでなく、庶民の間にも広がりました。8代将軍徳川吉宗が飛鳥山や隅田川堤、小金井堤などに桜を植えたことで、庶民も桜を楽しみながら宴を開くようになったのです。
この時代には、「花より団子」という言葉が生まれ、桜を眺めるだけでなく、食事やお酒を楽しむこともお花見の大切な要素となりました。当時の料理本には、華やかな弁当や団子のレシピが記されており、これが現代のお花見弁当の原型とされています。また、この時代に誕生した桜の品種「ソメイヨシノ」は成長が早く、全国に広がり、今ではお花見の主役となっています。
明治以降 – 現代のお花見スタイルへ

明治時代(1868〜1912年)以降、日本が近代化を進める中で、桜の木をもっと増やそうという動きが広がりました。このころ、成長が早く美しい「ソメイヨシノ」が全国に広がり、各地に現在のような桜の名所が誕生しました。また、お花見は観光資源としても注目され始め、多くの花見客を迎えるためのイベントやサービスが発展していきました。
戦後、桜は日本の復興の象徴となり、国民にとって特別な存在となりました。こうしてお花見は、春の訪れを祝う日本人にとって欠かせない行事として、現在まで受け継がれています。
日本のお花見文化を楽しむための準備とマナー
日本の春を象徴する「お花見」は、桜を眺めるだけでなく、日本の文化を体験できる特別なイベントです。桜並木を散策したり、ライトアップされた夜桜を眺めたり、色鮮やかなお弁当を広げてピクニックをしたりするのがお花見の魅力です。また、桜を背景に写真を撮ったり、和菓子や抹茶など日本ならではの味わいを楽しめば、さらに思い出深い体験になります。
ただし、お花見を楽しむためには、事前の準備やマナーが大切です。初めてのお花見でも安心して過ごせるよう、準備のポイントやマナーをご紹介します。
下見で良い場所を探す
お花見を成功させるには、事前の下見が大切です。良い場所を確保するために、桜の名所をいくつか選び、実際に訪れて比べてみましょう。参加人数に合ったスペースや桜の見え方を確認し、地面の状態もチェックしておくと安心です。
また、トイレの場所や会場のルール(火の使用やペット可否)を事前に確認しておきましょう。
快適に過ごせる服装を用意する
春の日本は天気が変わりやすく、昼間は暖かくても夜は冷えることがあります。特に夜桜を楽しむ場合は、ストールやひざ掛けを持っていくと安心です。
また、お花見では地面に座ることが多いため、汚れにくく動きやすい服装がおすすめです。ストレッチ素材のパンツや、薄手のアウターを準備すると、快適に過ごせます。
花粉症対策をしっかりする
桜の季節は花粉が多い時期でもあります。花粉症の人は、マスクを着用するだけでなく、静電気が起きにくい服を選ぶと花粉の付着を減らせます。
また、髪が長い場合はまとめておくと効果的です。特に風の強い日は花粉が多く飛ぶため、アレルギー薬を準備しておくと安心してお花見を楽しめます。
当日は早めに行動して場所を確保する
お花見当日は、良い場所を確保するために早めに到着することが大切です。もし希望の場所が取れなかった場合でも、下見で見つけた他の候補地に移動すれば安心です。
また、参加者が迷わず合流できるように、明るい色の服や目立つアクセサリーを身につけると便利です。
周囲に配慮してお花見を楽しむ
お花見はリラックスして楽しむ場ですが、周囲への配慮も大切です。日本では公共の場では静かに過ごすことが基本のマナーとされています。特に、お酒を飲むと声が大きくなりがちなので、他のグループに迷惑をかけないよう気をつけましょう。
また、日本ではゴミをその場に残さず持ち帰るのが習慣です。事前にゴミ袋を用意して、会場をきれいに保つよう心がけましょう。
まとめ
お花見は、日本の春の魅力を存分に味わえる行事です。桜を楽しむだけでなく、自然や人とのつながりを感じられる特別な時間でもあります。桜の下で過ごすひとときは、春の訪れを祝う素晴らしい体験。準備とマナーを大切にしながら、心に残るお花見を楽しんでください。