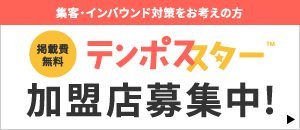ランキング
2025/01/27
神奈川(鎌倉)でやるべき10のこと

この記事の目次
神奈川(鎌倉)でやるべき10のことを紹介します。
鎌倉大仏

1243年初代の大仏は木像で金箔がつき、40メートルもあったそうです。台風により崩壊したため、現在の青銅製になり座る形になったそうです。約13.35メートル、総重量は約121トンもあり国宝になっています。存在感があり神秘的な雰囲気も感じさせる大仏様は、鎌倉のシンボルともなっています。胎内に入ることもできるので貴重な体験をしてみてください。

秋になると紅葉と大仏の日本らしい美しい景色が見られます。
円覚寺

1282年中国から来た無学祖元禅師によって創建された禅宗寺院です。「円覚寺舎利殿」は15世紀頃に建てられたそうで、神奈川県唯一の国宝建造物になっています。「方丈」は普段から入ることができます。池のある美しい庭園には椅子があるのでゆっくりと過ごすことが出来ます。「洪鐘」は、国宝に指定されていて鎌倉三名鐘のひとつで関東で最も大きい鐘です。
明月院

1160年は「明月庵」の名で戦死した父の供養の為に創建したとされています。明月院はあじさい寺と呼ばれており、境内には約2500株のあじさいが生育しています。そのうち9割が日本古来の品種であるヒメアジサイです。紫やピンクなどの色の花が咲いてとても綺麗です。6月から7月にかけてが見どころです。「花想い地蔵」も人気で、人や物との悲しい別れで傷ついた人の心を癒すやさしいお地蔵様と言われています。
長谷寺

鎌倉幕府より450年も前の736年に開創した、鎌倉有数の古寺で、奈良の長谷寺に対して、「新長谷寺」と呼ばれていたそうです。人気は「良縁地蔵」です。さまざまなお地蔵様がおりますが、互いに寄り添っている姿が印象的な、3体セットのお地蔵様です。境内の3か所に設置されており、すべて見つけられると良いご縁に恵まれるという言い伝えがあります。

「観音堂」には日本最大級の木造観音、十一面観世音菩薩が安置されています。
江ノ電鎌倉高校前

江ノ電の歴史は、1902年に江之島電気鉄道(現 江ノ島電鉄株式会社)が開業し、東海道線の藤沢停車場と江の島を結ぶ藤沢〜片瀬間でした。1903年に線路が伸び「日坂駅」の名で開業し、1953年に今の「鎌倉高校前」と改称されました。江ノ島と富士山、そして江ノ電を同時に見ることができ、最高の景色が見れます。人気のアニメ「スラムダンク」のオープニングシーンに登場する踏切が鎌倉高校前駅から七里ヶ浜方面に100mほど歩いたところにあり、人気のスポットです。
鶴岡八幡宮

1063年に、源頼義が戦勝祈願で、京都の石清水八幡宮を由比ヶ浜に勧請して祀ったことが起源とされており、源頼朝公が1180年に現在地へ移し、1191年に現在の「鶴岡八鶴岡八幡宮」になったそうです。重要文化財の「本宮」「若宮」があり大石段の上にある本宮と、大石段向かって右手にある若宮の上下両宮です。

「鳥居」が三つあり大きいのが特徴です。海に近いところにある「一ノ鳥居」JR鎌倉駅東口を出て3分のところにある「二ノ鳥居」鶴岡八幡宮の参道の先にある「三の鳥居」です。
銭洗弁天

災害が続いていた頃、源頼朝が1185年、巳年の巳の月・巳の日に「宇賀福神」からのお告げを夢で受け創建されたそうです。貧困の庶民のため源頼朝が祈願し、世の中の混乱が収まったと言われています。

「銭洗水」でお金を洗うと金運がアップすると言われており、まず本宮で身を清めて銭洗い用のザルを借り、奥宮で湧き出る「銭洗水」でザルにお金を入れ洗います。洗ったお金は清められ、福を呼びます。貯めこむより使った方がご利益があると言われています。
報国寺

1334年に高僧の天岸慧広が開山した臨済宗建長寺派の寺院です。本堂の周りには立派な枯山水(水を使わず、石・砂などで風景を表現する日本庭園)もあり、四季折々の花が咲きます。

2000本が並ぶ竹林の「竹の庭」があり、マイナスイオを浴びることができ、綺麗で圧巻です。緑の苔もとても風情があります。「ミシュラン・グリーンガイド」で、星3つを取得した寺院でもあります。「休耕庵 」では竹を見ながらお抹茶を飲むこともできます。
佐助稲荷神社

源頼朝は幕府を開き初期の目的達成のお礼として、1190年にここを霊地とし稲荷の社殿を創建したそうです。参道には沢山の朱の「鳥居」が立ち並んでおり見所の一つです。「白狐」がいたるところに置かれています。一説によると、開山良忠上人が子どもに虐められていた子狐を助けたところ、親狐が夢に現れ人の病を直す薬草の種を授かったとされ、白狐を供えて願を掛けるようになったと言われています。
建長寺

1253年に北条時頼により創建されたそうです。日本最初の禅宗の専門道場で、「建長汁(けんちん汁)」が生まれた寺でもあります。(けんちん汁とは肉や魚を使わず野菜と醤油を使った汁物で、日本の有名な料理です。)「三門」は1775年に建立し、国の重要文化財になっています。二重門は重厚感があり壁や門扉がなく、仁王像などを置ず簡素な作りで、禅の世界を表現しています。
まとめ

「神奈川(鎌倉)でやるべき10のこと」を紹介しました。鎌倉で有名な「鎌倉大仏」から始まり、昔ながらの神社や寺院が沢山あります。四季折々の景色、風情があり、海と自然と日本らしさが共存した鎌倉の地をぜひ満喫して下さい。着物体験ができる場所もあるのでフォットジェニックにもってこいです!